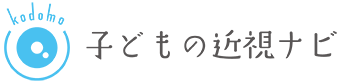ストレスが引き起こす“心因性視力障害”ってなに?

それが今回のテーマ、「心因性視力障害」です。
心が原因で目が悪くなるなんて、そんなこと本当にあるの?と疑う方もいるでしょう。
でも兵庫県で新見眼科など5軒の眼科医院を運営する医新会理事長・新見浩司先生によると、心因性視力障害は決して珍しいものではなく、「学校検診をすると、クラスに必ず一人はいます」とのこと。
7歳~12歳(特に9〜11歳で好発)に多く、男児より女児の方が約2〜4倍多いとされる心因性視力障害は、普段は特段の支障なく暮らしているのに、いざ視力を測ると、矯正が必要なほど低い結果になります。
それは決して仮病ではなく、視力検査のときは本当に見えていないのです。
心因性視力障害の原因は心理的ストレスです。
そのため、無邪気な未就学児や低学年よりも、心がより複雑になってくる10歳前後で多くなるようです。
子どもの場合、親子やきょうだい間の問題や、いじめ、虐待、友達や先生との人間関係、勉強や運動の不振など、様々な要因で精神的葛藤や欲求不満が大きくなり、心因性視力障害につながる場合があります。
しかし、これはやや教科書通りの答えであると新見先生は言います。
「多くの場合、原因は単純な“緊張”です。子どもにとって、視力検査という特別な状況は、バッターボックスに立たされているようなもの。普段はスラスラと本を読んでいるのに、教室で指名されると教科書がまともに読めなくなるようなタイプの子は、視力検査の場でも目の筋肉が過緊張状態になり、ピントが合わせにくなります。緊張が強くなると近視が強く出るだけではなく、“らせん状視野狭窄”や“管状視野狭窄”といって視野が狭くなることもあります」
もちろん、根深い心のストレスがそうした過緊張を引き起こす場合もあります。
そういう根本的な問題がある場合はそれと向き合い、心療内科や精神科の受診が必要となることもありますが、多くは“視力検査という場”に対する単純な緊張が多いのだそうです。
特に内向的で真面目、そして自己表現が苦手な性格のお子さんに、そうした傾向が見られやすいのだとか。

心因性視力障害が疑われる場合、やってはいけないのは、学校検診での悪い結果を鵜呑みにして、すぐに眼鏡屋さんへ走ってしまうこと。
眼鏡屋さんでの視力検査でもやはり緊張して視力が出ないと、普段は問題なく見えているのにもかかわらず、とんでもなく度の強いメガネを作られてしまうことがあるからです。
学校検診の視力検査で悪い結果が出たら、まず眼科専門医で詳しく調べてもらいましょう。
特に視能訓練士さんがいる眼科医がおすすめ。
心因性が疑われる場合、視能訓練士さんは「このレンズを入れると、よく見えるようになるからね」と子どもに声をかけながらリラックスさせ、マイナスのレンズとプラスのレンズを組み合わせて、わざと±0の伊達メガネ状態でかけてみたりします。
そうした検査テクニックにかかれば、わかりにくい心因性視力障害もすぐに判明するというわけです。
心因性視力障害は、もしも原因となっている根本的な心理的ストレスがあるのであれば、それに対処することが第一。
でも単純に緊張しやすいタイプの場合は、視力検査の前日に保護者が家で、視力検査表を使って練習させてあげるのがいいでしょう。
視力検査に限らず、もう少し成長すれば、様々な場面での緊張の解き方もおのずと習得できるものなので、それまではぜひご家族の方がサポートしてあげてください。
〈参考文献〉
新見浩司・監修『お医者さんがすすめる視力回復 本物の「目の体操」7日間メニュー』(2013年、リンケージワークス)
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
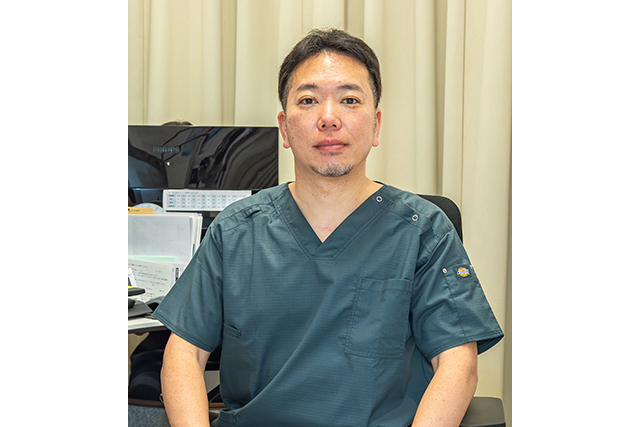
近視医療の女王・大野京子医師 特別インタビューその①
大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大事な子どもの視力を守る先行投資」
- 最新の治療に目を向けていただきたい 今年7月に放映された人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS/TBS系)で取り上げられた眼科医の大野京子先生(東京医科歯科大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長)は、アジア太平洋眼科学会で“Queen of Myopia(近視医療の女王)”として表彰された、小児の近視治療のリーダーのひとりです。大野先生は「子どもたちの大事な視力を守るために

関連記事
市販の目薬は、基本的に子ども用なら大丈夫だけど……
子どもに使わない方がいい目薬もあるってホント?
- こんなにたくさんあると、どれを選べばいいのか悩んでしまいます。今日も街のドラッグストアには、たくさんの目薬が並べられています。子ども用から大人用、アレルギー、疲れ目、ドライアイ、充血、ものもらい用などなどなど。それに、対象年齢や使用目的は同じでも、各製薬会社が競うようにさまざまな銘柄をリリースしていますよね。こんなにたくさんあると、どれを

専門医が教える、色覚異常の真実
子どもが「色覚異常」だったら、どうすればいいの?
- 日本人の男性20人に1人の割合でいることが知られています。かつての学童健診では、毎年おこなわれる視力検査とともに、小学校1年生時と4年生時には必ず色覚検査がおこなわれていました。しかし全員を対象とした色覚検査は2003年をもって廃止され、以降は希望者のみに実施されるようになります。どうしてだと思いますか?兵庫県で5つの眼科医院を運営する医